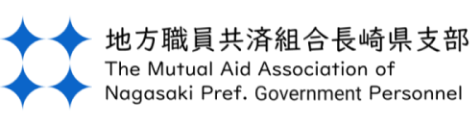短期給付事業は、民間における健康保険制度に相当するもので、組合員とその家族(被扶養者)の公務によらない病気やケガ、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付事業です。
この短期給付事業は大きく分けて、保健給付、休業給付、災害給付の3 つからなり、それぞれに、地方公務員等共済組合法で定められた「法定給付」と各共済組合独自の「附加給付」があります。
なお、給付事由が発生してから2年以内に給付請求を行わないと、給付が受けられませんのでご注意ください。
法定給付とは
地方公務員等共済組合法によって給付の内容、条件、給付額等が定められ、各共済組合が共通して行うもので、次の3種類に分けられます。(法第53 条)
| ① | 保健給付 | 組合員と被扶養者が公務外の病気やケガ、出産、死亡のとき |
| ② | 休業給付 | 組合員が公務外の病気やケガなどやむを得ない事由で休業し、給与が減額されたとき |
| ③ | 災害給付 | 組合員または被扶養者が非常災害で死亡したり、住居や家財に損害を受けたとき |
附加給付とは
法定給付を補完する目的で、各共済組合が財政状況を考慮して独自に行う給付で、その具体的な給付の内容、条件、給付額等は各共済組合の定款で定められ、通常「法定給付」に上乗せして支給されます。(法第54 条)
短期給付の種類
短期給付の種類は、 地方職員共済組合本部「短期給付とは」 をご覧ください。
※ 上図のなかで一部負担金払戻金は、組合員が負担した費用を払い戻すものであり、法令上、附加給付ではありません。(便宜上、附加給付等欄に記載しています。)
請求手続きについて
◆請求手続き ~不要~
医療機関等の窓口でマイナ保険証等を提示し、診療を受けたときの給付
組合員(被扶養者)が窓口で直接医療機関等に支払う額は、一般的な例として、医療費の3割(所得、年齢によって自己負担割合が変わります)となります。残る費用は共済組合負担となり、共済組合が医療機関等に支払います。
窓口での自己負担が一定額以上になったときは、高額療養費や一部負担金払戻金、家族療養費附加金が自動で給付されます。
◆請求手続き ~必要~
給付金を請求するときは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出してください。給付事由が生じた日の翌日から2年以内に請求しないと、給付金が受け取れなくなります。
請求手続きが必要な「主な」給付
- 病気になったとき
療養費(家族療養費)・・やむを得ない理由で医療費の全額を支払ったとき
移送費(家族移送費)・・症状が重く緊急やむを得ず医師の指示で移送されたとき - 出産したとき
出産費(家族出産費) - 死亡したとき
埋葬料(家族埋葬料) - 休業し、給与が減額されたとき
傷病手当金・・公務によらない病気やけがで休業したとき
出産手当金・・出産に伴い休業したとき
休業手当金・・家族の病気やけがなどの理由により欠勤したとき
育児休業手当金・・育児休業したとき
介護休業手当金・・介護休業したとき - 災害にあったとき
災害見舞金・・非常災害で住居や家財に損害を受けたとき
弔慰金(家族弔慰金)・・非常災害で死亡したとき
※制度の詳細、支給要件、請求手続きなどについては、保険給付・休業給付・災害給付のページをご覧ください。