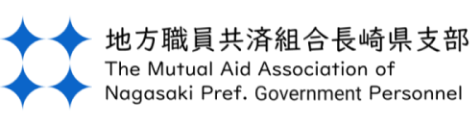病気やケガをしたとき
組合員またはその家族(被扶養者)が公務によらないで病気やケガをしたときは、病院の窓口でマイナ保険証(マイナンバーカードを取得していない方や、マイナ保険証の利用登録を行っていない方は資格確認書、もしくは組合員証(令和7年12月1日まで))を提示して自己負担分を支払えば、必要な医療を受けることができます。

医療費総額

7割 共済組合負担(療養費・家族療養費)

3割 組合員負担※
※義務教育就学前の被扶養者の自己負担割合は2割です。
※70~74歳の組合員および被扶養者の自己負担割合は2割です(一定以上の所得者を除く)。
- 医療費の共済組合負担(療養費・家族療養費)
医療機関等の窓口でマイナ保険証等を提示することで、自己負担分のみの支払いで診療を受けることができます。
緊急その他やむを得ない事情でマイナ保険証等を使用できなかったときなどは、診療等にかかった費用を本人が一時的に立て替え、その後共済組合に請求し、共済組合が必要と認めたときは、自己負担分を控除した残りの額が共済組合から療養費または家族療養費として支給されます。 - 入院中の食事代
組合員やその家族である被扶養者が入院中に食事の提供を受けるときは、1食につき490円を自己負担し、残りは共済組合から入院時食事療養費として支給されます。 - 医療費が高額になったとき
窓口での自己負担が一定額以上になったときは、高額療養費や一部負担金返戻金、家族療養費附加金が自動で給付されます。
なお、あらかじめ共済組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、保険医療機関の窓口に提示すれば、高額療養費に相当する部分は共済組合から病院に直接支払われるため窓口での負担を低くおさえることができますが、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

交通事故など他人(第三者)の加害行為でケガ・病気になったときは、その治療に要する費用は、加害者である第三者が最終的に負担することになります。
他人(第三者)の加害行為で医療機関を受診した場合、マイナ保険証等を使用して治療を受けることもできますが、マイナ保険証等を使用した場合の医療費は、共済組合が一時的に立て替えたものですので、共済組合から加害者へ請求を行う必要があります。
共済組合が加害者への請求を行うためには、加害者の情報を得る必要があることから、他人(第三者)の加害行為で医療機関を受診し、マイナ保険証等を使用した場合は、速やかに下記の相談室(共済組合外部委託先)に連絡してください。
フリーダイヤル: 0120-732-255 ㈱オークス 第三者行為相談室
移送されたとき
組合員またはその家族(被扶養者)が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、移送費または家族移送費の支給を受けることができます。
- 移送により適切な保険診療を受けたこと
- 療養の原因である負傷、疾病により著しく移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
移送費(家族移送費)の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用として算定した額です。
出産したとき
組合員またはその家族(被扶養者)が出産したときには、1児につき 500,000円※ が支給されます。これを「出産費」(被扶養者の場合は「家族出産費」)といいます。
※産科医療補償制度 に加入する医療機関等の医学的管理下の場合は 500,000円、制度未加入機関等での出産の場合は 488,000円となります。

- 妊娠4月以上(85日以上)で母体保護法に基づく人工妊娠中絶を行った場合にも支給されます。
- 窓口負担を軽減する制度「直接支払制度」をご利用ください
直接支払制度とは、出産費・家族出産費の額を上限として、共済組合から医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。多額の現金を用意しなくても安心して出産できるようにと創設されました。
(医療機関によってはこの制度を利用できないことがあります。)
出産の際に、医療機関等でマイナ保険証等を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。なお、出産費用が出産費・家族出産費の支給額より少ない場合は、差額が当共済組合から支給されます。また、退職後でも被保険者として継続して1年以上の加入期間があり、退職後6カ月以内の方は出産費を受けることができます。
医療機関等に直接出産費が支払われることを希望しない方は、申請手続きを行ってください。この場合、一旦全額を医療機関等にお支払いいただくことになります。
死亡したとき
○埋葬料・家族埋葬料・・・・・組合員または被扶養者が公務によらないで死亡したときに請求
<添付書類>
・埋葬許可証または火葬許可証の写し
※組合員が死亡した場合、実際に埋葬を行った者が請求する場合は、費用の額に関する証拠書類(領収書など)が別途必要です。