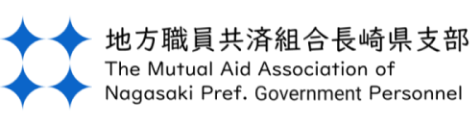目次
資格に関すること
-
退職後も組合員として共済組合に加入することはできますか?
-
退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職日から20日以内に共済組合に「任意継続組合員申出書」を提出することにより、「任意継続組合員」として、短期給付(休業給付を除く。)及び福祉事業の一部について、2年間を限度に在職中と同様の適用を受けることができます。
-
75歳以上の後期高齢者医療被保険者は、共済組合の加入対象になりますか?
-
共済組合の加入要件を満たす場合は、共済組合員になります。
後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、一部の短期給付及び福祉事業が適用されます。 会計年度任用職員(フル12月超)は、上記以外に民間の企業年金に相当する退職等年金給付事業が適用されます。
資格確認書に関すること
-
マイナ保険証を使っていますが、念のため「資格確認書」を持っておきたいので、発行してもらえますか?
-
資格確認書は、マイナ保険証を利用できない状況にある場合に交付するものです。
マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情がない場合は、交付できません。
-
退職した場合に「資格確認書」はどうすればよいですか?
-
退職後に在職時の資格確認書で受診することを防ぐため、資格確認書の回収にご協力をお願いいたします。なお、資格のなくなった資格確認書で受診された場合は、後日、医療費を返還請求されますのでご注意ください。
-
マイナンバーカード紛失により個人番号が変わりました。共済組合に届出は必要ですか?
-
マイナンバーカードの紛失等により、組合員又は被扶養者の個人番号が変更になった場合は、「個人番号変更に関する申告書」を所属所経由で共済組合へ提出してください。
-
マイナ保険証について
-
マイナ保険証についてのよくある質問は、厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問」をご覧ください。
標準報酬に関すること
-
標準報酬月額がわかりません。どのようにしたらわかりますか?
-
標準報酬月額は短期給付・長期給付・掛金負担金等、算定の基礎となる額です。給与明細書で確認できます。
-
4月から産休中のため、他の期間に比べて報酬の額が少なくなっています。この場合であっても4月から6月までの報酬により標準報酬を決定することになりますか。
-
4月から6月までの間に産前産後休業を取得する場合、報酬額によっては、その後の育児休業手当金等の給付額が少なくなることがあります。このようなときは、産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬の平均額(以下「年間報酬の平均(産前産後)」といいます。)により標準報酬を決定することができます。詳細は、こちらのお知らせをご覧ください。
ただし、この決定を行うためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。
- 4月から6月までの間に産前産後休業を取得していること。
- 4月から6月までの報酬を基に算定した標準報酬と年間報酬の平均(産前産後)によって算定した標準報酬に、2等級以上の差があること。
- 年間報酬の平均(産前産後)で標準報酬を算定することについて、組合員本人から申出があること。
-
随時改定に該当にするか、しないかは、組合員が自身で確認・判断しなければならないのですか。また、自分で行うべき手続きもあるのですか?
-
給与支給機関において判断しますので、組合員の方の手続きは必要ありません。
-
病気休職中(無給)や育児休業中に固定的給与に変動があった場合は、随時改定の対象となりますか?
-
休職等が終了し職場に復帰した月(月の途中の場合はその翌月)を「変動があった月」として、以後の3か月間の報酬の平均により、随時改定に該当するか判断します。
-
給与改定が遡及して行われたとき、随時改定は行われますか?
-
給与改定が遡及して行われたときは、給与改定後の額が実際に支給された月を「変動があった月」として、以後の3か月間の報酬により、随時改定に該当するか判断します。
【例】4月に遡及する給与改定があり、12月に、給与改定後の給料(12月分の差額が12月末までに支給された場合も含む)と給与改定による差額(4月~11月分)が支給された場合
12月を「変動があった月」として随時改定に該当するか判断します。
なお、給与改定による給料の差額(4月~11月分)は除いて、固定的給与に変動があった月から継続した3か月間の報酬の合計を算定します。
-
「随時改定」と「育児休業等終了時改定」の違いはどのようなものですか?
-
「随時改定」と「育児休業等終了時改定」を比較すると、次のように改定の要件が異なります。
- 随時改定を行うためには2等級以上の差が必要ですが、育児休業等終了時改定は1等級以上の差 があれば改定できます。
- 随時改定は変動があった月以後3か月間の報酬の支払基礎日数がいずれも17日以上であることが必要ですが、育児休業等終了時改定では支払基礎日数が17日未満の月がある場合であっても、改定を行うことができます(この場合、支払基礎日数が17日未満である月を除いて算定します。)。
→月の途中で職場復帰した場合、育児休業等終了時改定の方が、早い月から標準報酬の改定を行うことができます。
- 育児休業等終了時改定には申出が必要ですが、随時改定の申出は不要であり、要件を満たしたときに改定が行われます。育児休業等終了時改定の申出を行わなかった場合でも、随時改定の要件を満たした場合は、随時改定が行われます。
-
「支払基礎日数」とは勤務日数ですか?
-
報酬の支払の基礎となった日数をいい、次の式により計算します。支払基礎日数は、欠勤等により報酬が支払われない日がある月に、その月の報酬を含めて報酬月額を算定することが妥当かどうか判断するための基準となります。
支払基礎日数=暦の日数-週休日-欠勤日
(祝日、年末年始の休日は、支払基礎日数に含めます。)
掛金に関すること
-
家族にも掛金はかかるのですか?
-
扶養家族も共済組合の給付を受けていますが、掛金はかかっていません。掛金は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても掛金は変わりません。
※介護掛金(保険料)も、40歳以上65歳未満の被扶養者分は、組合員徴収分に織り込まれているため、直接徴収されることはありません。
-
現在、入院中のため、傷病手当金を受給しています。入院中は、給料は支給されないのですが、この間も掛金は支払うのでしょうか。
-
組合員になっている限り、給料の支払いがなくても掛金は支払う必要があります。また、欠勤する前の掛金を基準として傷病手当金の額が算定されます。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、欠勤4日目から、1日につき支給されます。
年金に関すること
-
年金について
-
年金制度についてのよくある質問は、地方職員共済組合本部の「年金相談Q&A」をご覧ください。